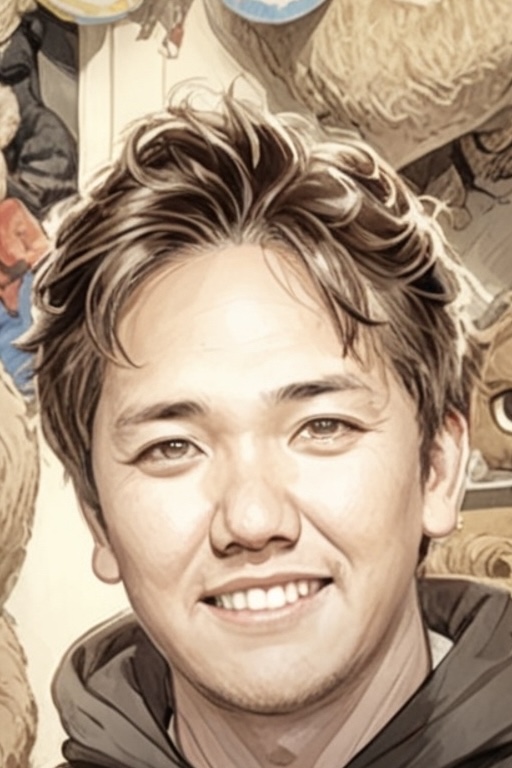外食をする。同居人も酒が好きなことからお互い仕事の日などはほとんど外食で済ませる。食事というか飲みに行ってる。家で飲んだらどれだけ安上がりなことか、とわかってはいるのに、店飲み、居酒屋飲み、ファミレス飲みを繰り返している。健康については言わずもがな、そこのコストが恐ろしい。個人的なエンゲル係数が人間における水分量くらいになってる気がする。エンゲル係数って食費だけだっけ。アルコール入れちゃいけないんだっけ。
そんなわけで、よりコスパの良い飲み方を探し求めているここ数年である。歳は重ねても結局飲むペースが変わらないし、質より断然量である。お前は大学生か新入社員かと思われるような店選び、飲み方をしている。結局酒量が抑えられない私みたいなバカは飲み放題が一番コスパがいい。一杯100円程度の頭の悪いハイボールを出すような居酒屋は置いておいて、500円程度するのがボリュームゾーンの店であれば、4,5杯で元は取れる。4,5杯なんてお通しだけで飲み干せる量だろ。
注意しないといけないのは時間制限があり、少しでもコスパよくしないとと考えた結果、呼吸をするようにアルコールを摂取して翌日なんら記憶がないなんて事態になることだ。コスパを求めるがあまり究極のタイムパフォーマンスを発揮してしまう。2時間飲んだ記憶がまるまるなくなるなんて、0分になったも同然である。何にお金を払ったんだ自分は。
他にも、飲み放題は食べ放題とのセットがノルマになっていることもある。アルコールの摂取量は若いころと変わらなくても、胃袋の大きさは加齢とともに小さくなっているものだ。食べ放題などと組み合わせられてしまったら、一気にコスパが悪くなってしまう。少しでも元をとろうと無理な注文を繰り返し、しばらくトイレにこもりきり、なんてことよくある。食べ物は適度につまみがあって、〆になにかしらの麺類が食べられれば十分なのである(ここはまだ多少若さがある)。
今後私のコスパのよい飲み方、居酒屋を紹介するシリーズ連載をしていく。先立って私の方針をここに記しておく。
はじめに
居酒屋は現代日本におけるオアシスであり、会社員の心を潤す水源である。だが、居酒屋の利用法を誤ると、財布は干上がり、翌朝は後悔の二日酔い砂漠に放り込まれる。そこで本稿では、居酒屋における「コストパフォーマンスよい使い方」を論じる。
飲み放題の効用
飲み放題は居酒屋界における「定額制サブスク」である。月額980円でアニメ見放題のように、2時間3,000円でドリンク飲み放題。理論的には30分で生ビールを4杯飲めば元が取れる計算だが、その時点で人類は「元を取った」より「正気を失った」状態に陥る。つまり、飲み放題はコスパ最強であると同時に、理性最弱の制度でもある。
しかし実際には、2〜3杯以上飲む人にとって飲み放題は圧倒的に有利であり、さらに「普段頼まない梅酒ソーダ」や「実験的なカルーアミルク」を試す好奇心も満たされる。飲み放題は経済合理性と遊び心の両立を可能にする、極めて日本的システムなのである。
食べ放題の限界
一方、食べ放題。こちらは一見夢の制度に見えるが、実態は胃袋という有限資源に縛られた戦場である。人は「今日は元を取るぞ」と意気込むが、30分後には唐揚げ2皿とポテトで戦線離脱。さらに「デザートもあるよ」と畳みかけられても、口は甘味を求めても腹がもう受け入れを拒否する。
したがって、食べ放題のコスパは極めて「条件依存型」であり、大人数でシェアする場合や「焼肉を浴びたい日」以外は非推奨である。
単品料理戦略
飲み放題に単品料理を組み合わせることは、いわば「最適化アルゴリズム」である。
例として以下の戦術を提案する。
前菜防御:枝豆・冷奴など低価格で長持ちする食品を配置。序盤の会話タイムをカバー
主力投入:唐揚げ・焼き鳥といった万人受けの兵力を展開。胃袋の満足度を最大化。
シメ統制:焼きおにぎり、出汁茶漬けで過剰摂取を防ぎ、会計を穏やかに着地させる。
これにより「食べ放題で撃沈するリスク」を回避しつつ、飲み放題の利点を最大限享受できる。
結論
居酒屋のコスパ最強戦略とは、「飲み放題」+「単品料理」のハイブリッドモデルである。食べ放題はイベント的な非日常にこそ映えるが、日常使いにおいては胃袋も財布も疲弊する。
結局のところ、居酒屋を賢く楽しむには「お酒で冒険、料理は堅実」というバランス感覚が求められるのだ。
最後に強調したい。居酒屋は戦場ではない。
元を取る場所ではなく、楽しむ場所である。
そう思いつつ、また次の飲み会でも「今日は絶対に元を取る!」と宣言してしまう自分がいる。