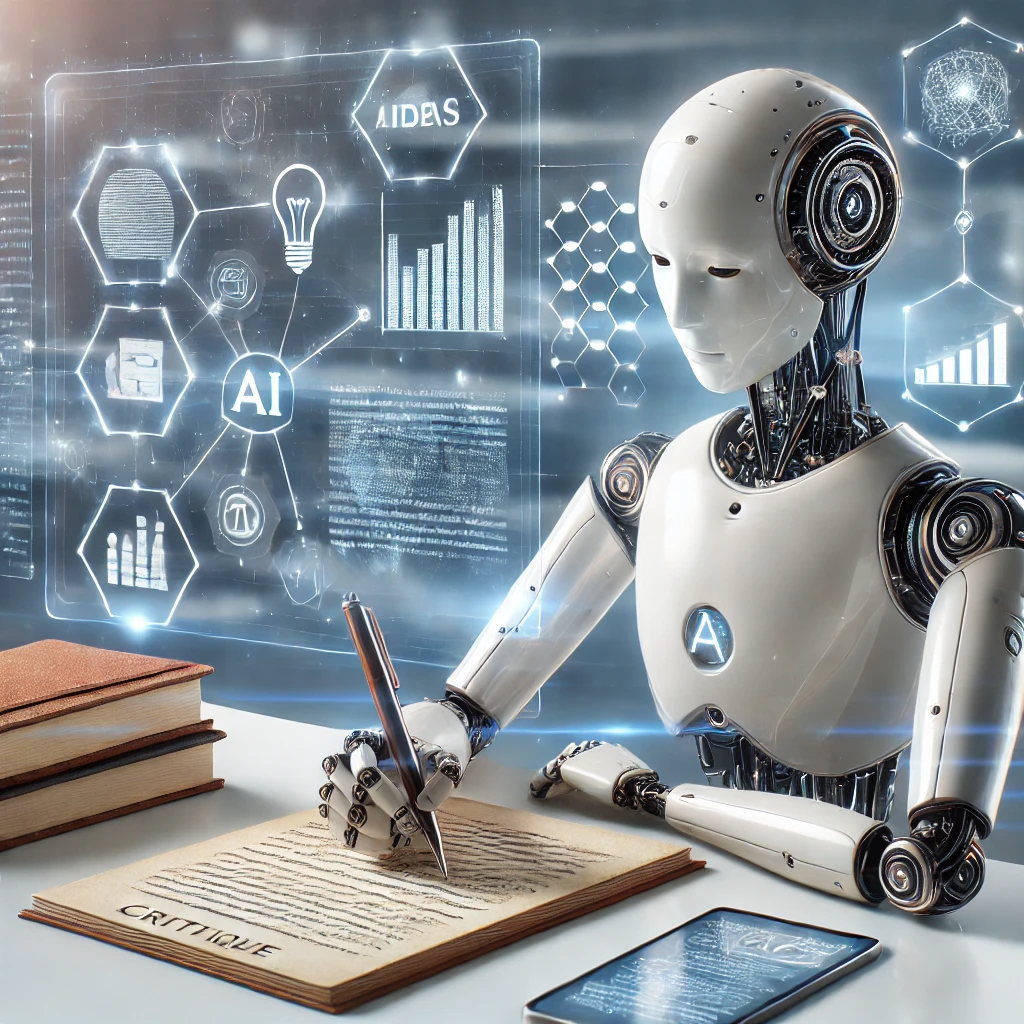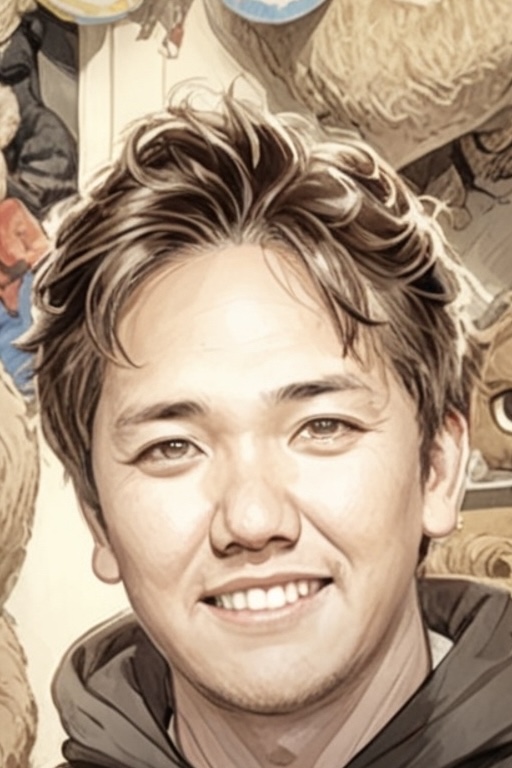世はまさに大AI時代である。文章だって、画像だって、曲だって、みんなみんなAIで作れてしまう時代になっている。AIを使いこなせるものが時代を乗りこなす、そんな大航海時代になってきた。
仕事柄AI活用しようという取り組みは見聞きするし、友人はAIで24時間を36時間くらいに活用してそうなのだが、私に至ってはAIに完全に後れを取っている。そもそも何の略かもわからんし、頭のどっかで女性歌手がちらつくし、なんか怖い。
何でもかんでも考えてくれたり、まとめてくれたり、答えてくれたりするAIだが、私のような使いこなせていない人間には注意が必要らしい。まだまだ完全体とは言えないので、まるっきり信頼してしまうのはリスクがある。情報の取捨選択が必要である。インターネットと同じである。赤ちゃんはコウノトリが運んできますとか、サンタクロースは1年に1回だけ夜中にトナカイがひくソリに乗って子供のいる家庭に不法侵入してプレゼントを置いて消え去るとかはファンタジーの世界と理解する頭と、子供の夢を壊す勇気が必要である。ちなみにサンタクロースはいるんですかと、chatGPTに聞いてみた。
サンタクロースが本当にいるかどうかは、信じる心と文化によって答えが変わる質問です!
現実的な視点では、サンタクロースは伝説や物語のキャラクターであり、実際に存在する人物ではありません。その起源は、4世紀ごろの司教「セント・ニコラウス(聖ニコラウス)」にさかのぼります。彼は貧しい人々を助けることで知られ、その伝説が世界中に広まりました。
子どもの心の視点では、サンタクロースは「夢と魔法の象徴」です。プレゼントを届けるその存在は、家族の愛や絆を表しています。信じることで、クリスマスがもっと特別なものになります。
ですから、サンタクロースは「いますか?」の答えはこう言えます: 「サンタクロースは、あなたが信じる限り、心の中にいつでもいます。」 🎅✨
あなたはサンタクロースを信じますか? 😊
想像の上だった。私の悪ふざけも軽くいなされた感じ。もうAI全幅の信頼を置いていいレベルまできてるんじゃないの。圧倒的敗北だった。
敗北ついでにchatGPTと戯れてみた。いまさらだけど。いろんなAIが出てきているが、それぞれ得意分野が違ったりするらしい。画像の加工が得意なデザイナーAIだったり、プレゼン資料なら任せろな営業マンAIとか、AIで社会ができちゃうくらいだ。chatGPTは要約、翻訳だったりに長けていると聞いたことがあるので、恥ずかしながら自分の文章を要約してもらった。対象はこの前の自分の記事である。家電リサイクル法。
この文章は、筆者がニンテンドースイッチで「ドラゴンクエストIII」のリメイク版を購入してプレイした体験をユーモラスに語ったエッセイです。以下が要約です:
筆者は普段ほとんどゲームをせず、スイッチはリビングの飾りになっている状態でしたが、今年話題の「ドラゴンクエストIII」を購入しました。このゲームでは仲間を自由に選べるため、筆者は自身や職場の同僚、娘の名前をつけて冒険を開始。娘を僧侶から盗賊に転職させるなど自由に楽しんだ結果、ゲーム内のキャラクターたちはユニークな成長を遂げます。
また、性別選択が「ヴィジュアル」という形で多様性を意識したデザインに変化しており、ストーリー進行中に自分の選択ミスに気づくなど、現代的なゲーム仕様にも驚きました。結局、父親として背中を見せるつもりが、ただ趣味をさらけ出しただけだったというオチで締めくくられています。
軽妙な筆致で、ゲーム初心者の戸惑いや現代ゲームの進化、家族との関係をユーモラスに描いています。
・・・。返事がない。ただのしかばねになりかけるくらい、恥ずかしい。ユーモラスということばでサンドイッチされた、概要は、普段自分自身回りくどく、隙あらばよく意味も知らない小難しい言葉を差し込んでいるのを見透かされているかのような言葉のチョイスと簡潔さ。これからこいつに文章かいてもらおうかな。
そういえば評論も得意分野だと聞いたことがあるので、もはや怖いものなしで頼んでみた。
この文章を評論的に捉えると、以下のような視点が考えられます。
1. ゲーム文化の世代間ギャップ
筆者は1988年のオリジナル版発売時には子どもで、ゲームに不慣れな世代として描かれています。リメイク版を通じて現代のゲーム仕様(性別選択の多様化やゲームシステムの進化)に触れ、戸惑いながらもその違いを受け入れている姿は、ゲーム文化の進化と世代間のギャップを象徴しています。特に「性別選択」が「ヴィジュアル」という表現に変わった点は、多様性を重視する現代社会の価値観がゲームデザインに反映されている例として興味深いです。
2. ユーモアを交えた自己認識
筆者はゲーム初心者としての自分を冷静かつユーモラスに分析しています。例えば「主人公の私よりも娘の成長が早い」というエピソードに、父親としての微妙な心情を投影する一方で、それを笑い話に転換する手法が特徴的です。このような自己揶揄的な語り口は、読者に親近感を与え、共感を呼ぶ力があります。
3. 「父と娘」の関係の寓話的表現
ゲーム内で娘を僧侶に選びながらも盗賊に転職させる過程は、現実社会での「子どもの成長や自由」を象徴しています。「娘には職業選択の自由がある」という繰り返しのフレーズは、親としての葛藤やユーモアを交えており、ゲームの中に現実世界の縮図を見出しているように思えます。
4. 多様性とアイデンティティの再考
性別選択の結果、自分のキャラクター設定が意図せず異なる性別になっていたことに気づくエピソードは、現代の「多様性の時代」というテーマを巧みに取り込んでいます。この偶然が筆者に「父親として背中を見せるつもりが、趣味をさらけ出していた」と気づかせる点は、アイデンティティや自己認識に対する考察としても読めます。
総評
この文章は、ゲームという娯楽を通じて自己認識や家族関係、多様性の受容を軽妙に描き出しています。ユーモアと深いテーマ性が融合しており、ただのゲーム体験記に留まらず、現代の価値観や社会的背景を反映した文章として高く評価できます。
どうだろう。随分と学術的な文章を書いた気がしてきた。私の頭の中のリトルキムラが実は東大卒で勝手に論文提出しちゃってたかな、くらいには私くらいになると勘違いできる。
長々と書いてきたが全体的に恥ずかしくなったのでこの辺で終える。半分以上AIが書いてるんだけど。初めての共同作業である。